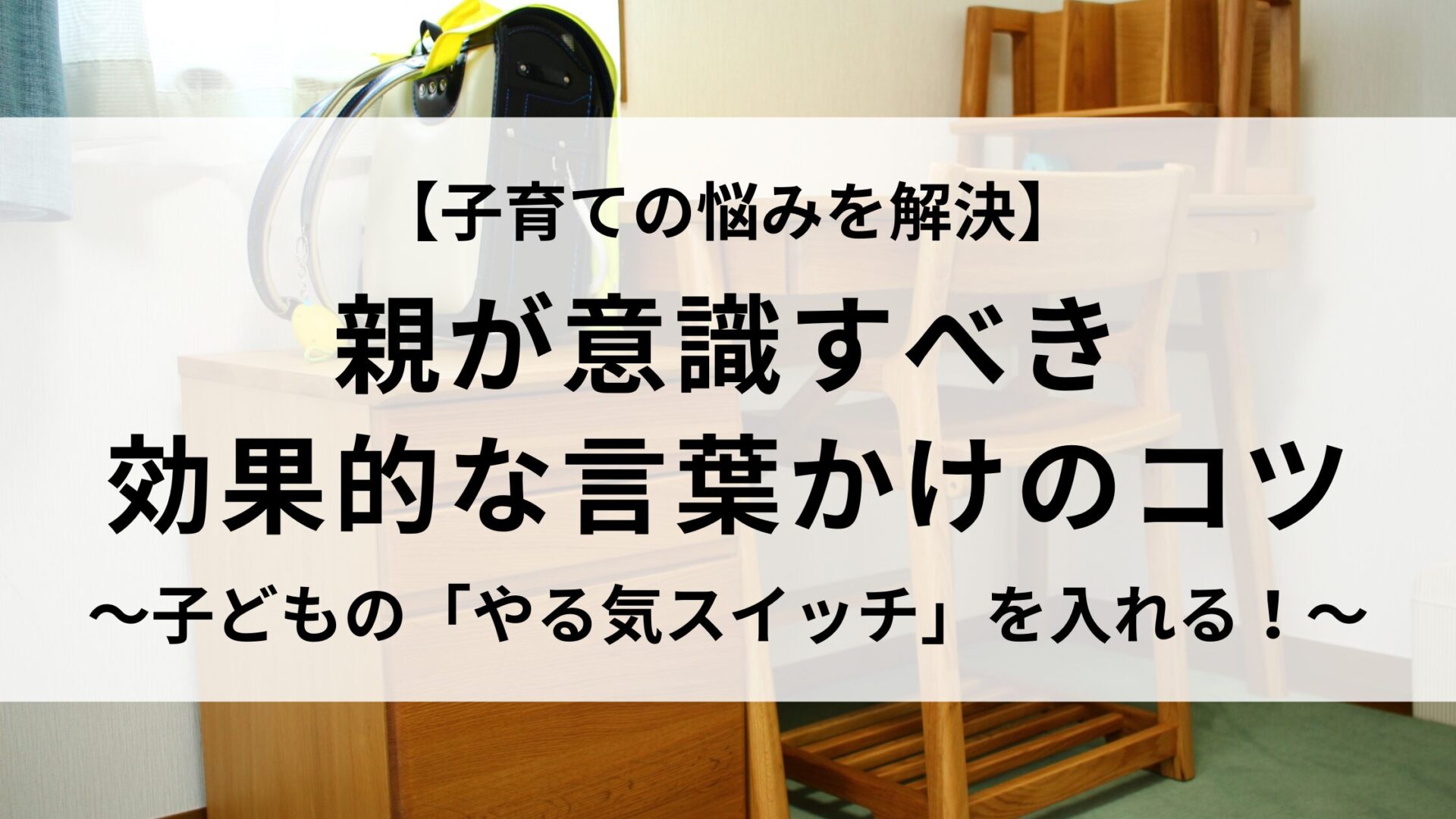はじめに
- 子どものやる気が続かない
- 少しの失敗で自信をなくしてしまう
- なかなか自分から行動しようとしない
こうした悩みは、多くの保護者や教育関係者が一度は抱えたことのある課題です。
子どもが本来持っている力を引き出し、成長を後押しするには、日々の関わり方が大きな鍵を握っています。
その中でも特に重要なのが、「言葉かけ」の工夫です。
幼児期から小学生の時期にかけて、子どもの脳と心は急速に発達します。
この時期にどのような言葉をかけられたかによって、やる気や自己肯定感、さらには将来の学びへの姿勢にまで大きな影響が及びます。ただし、声をかければ何でも良いわけではありません。
親や先生の言葉が、子どもの行動や思考にどう作用するのかを理解し、適切なタイミング・内容・伝え方を工夫することが求められます。

たとえば、同じように「がんばったね」と伝える場合でも、その言葉が「親が求める結果に応えたことへの評価」なのか、「子ども自身の努力や工夫を認めたもの」なのかによって、受け取り方は大きく変わります。
子どものやる気を引き出すには、言葉の内容だけでなく、そこに込められた“意図”や“意味づけ”が非常に重要になります。
また、子ども一人ひとりには異なる特性や個性があり、同じ声かけがすべての子に効果的とは限りません。
大切なのは、「この子には、どんな言葉が届くのか」を意識することです。
子どもの行動の背景を理解し、共感的な姿勢を持つことで、言葉の力はより大きく発揮されます。
本記事では、子どものポテンシャルを引き出す声かけの考え方と実践方法をわかりやすく解説していきます。
日々の子育てや教育の現場で活かせる、具体的で再現性のある言葉の工夫をお届けします。
目次
なぜ“言葉かけ”が子どものやる気と才能に影響するのか

子どもにとって、大人からかけられる言葉は“評価”であると同時に、 “自分自身の認識”をつくる材料でもあります。
特に未就学児から小学生にかけては、自己イメージが形成される重要な時期であり、この時期にかけられる言葉は、子どもの自己肯定感や学びへの意欲、挑戦する姿勢に直結します。
教育心理学では、外からの言葉が「内的対話」へと変化していく過程が注目されています。
たとえば、ある子が失敗したときに「どうしてできなかったの」と言われ続けると、その言葉が内面化され、自分自身に対しても「できない自分はダメなんだ」と繰り返すようになります。
一方で、「失敗してもいいから挑戦したね」「考え方がよかったよ」と言われた子は、自分の行動に意味を見出し、自ら次の一歩を踏み出す力を養っていきます。
つまり、子どもの才能や可能性は、その子自身の中に眠っているだけでなく、大人の言葉によって引き出されるものでもあるのです。
声かけは単なる励ましではなく、子どもにとっての“思考の枠組み”そのものをつくる、極めて影響力の大きい関わり方だといえます。
脳と心が発達する時期に必要な「親の言葉の力」
幼児期から小学校中学年ごろにかけて、子どもは自分の感情や考えを言葉にできるようになり、同時に周囲からの評価を受け入れる柔軟性を持ち始めます。
この時期は、脳の可塑性が高く、経験によって思考や感情のパターンが形成されやすい特徴があります。
このときに大人がどんな言葉をかけるかによって、子どもの脳は「自分はできる」「挑戦することは楽しい」といった前向きな回路をつくるか、それとも「自分はダメだ」「間違うことは恥ずかしい」といった否定的な回路を強化するか、大きく分かれてしまいます。
重要なのは、結果や成績だけを評価するのではなく、プロセスや努力に目を向けた言葉をかけることです。
親や教師の一言が、子ども自身の“ものの見方”を形づくり、その後の学びや行動に深く関わっていくことを、私たちは常に意識する必要があります。
やる気を削ぐ言葉・伸ばす言葉の違いとは
一見すると励ましに聞こえる言葉でも、実は子どものやる気を奪ってしまうケースがあります。
たとえば、「もっとがんばってね」は、すでに頑張っている子にとっては「まだ足りない」と捉えられ、無力感や不満を残す可能性があります。
逆に、「さっきより集中できてたね」「今日はここまでやれたことがすごいね」といった言葉は、子どもの中にある“できた実感”を強化し、次の行動を後押しします。
このように、具体性がある声かけは、自己評価とやる気の循環を生み出しやすくなります。
言葉かけの目的は、大人の期待を伝えることではなく、子ども自身が「もっとやってみよう」と思える状態をつくることです。
だからこそ、言葉をかける側の意図よりも、子どもがどう受け取るかという“反応の質”に注目することが大切です。
子どものやる気を高める言葉かけの基本
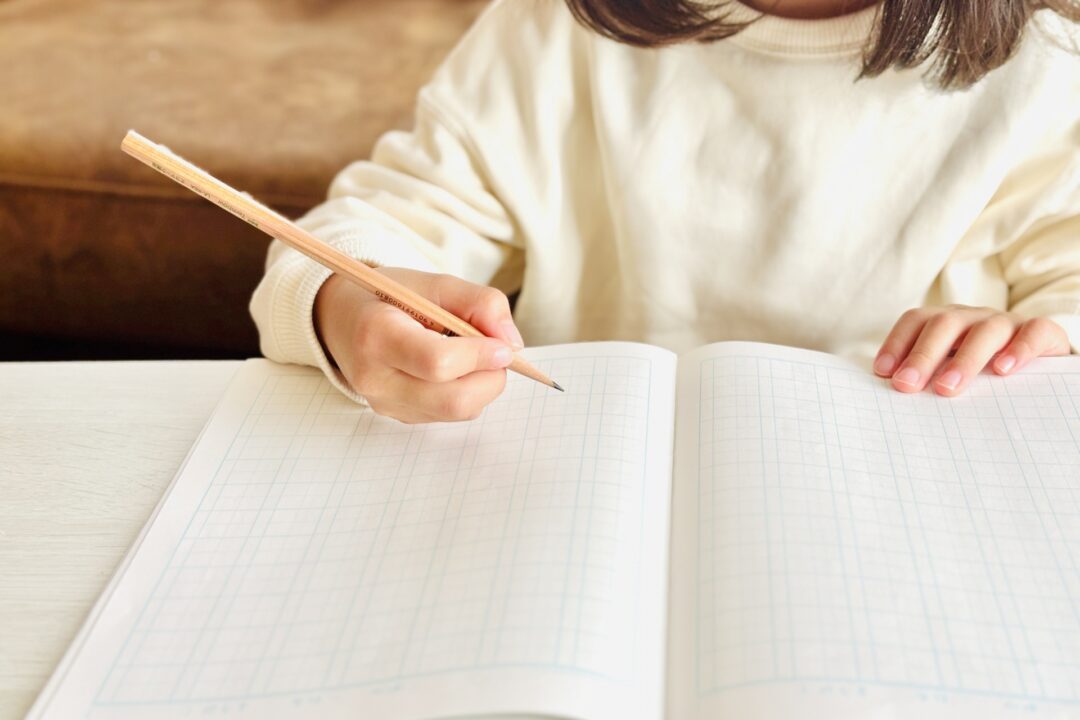
やる気を高めたいと願う保護者や教育関係者にとって、日々の言葉かけは最も身近で強力なアプローチです。
ただし、効果的な声かけには“順序”と“視点”があります。子どもに期待を伝えることは大切ですが、その前に「何に注目して、どのように言葉にするか」を見直す必要があります。
基本となるのは、結果ではなく、行動やプロセスへの注目です。
なぜなら、結果は必ずしも子ども自身の努力だけで決まるものではなく、運や環境の影響も大きいためです。
一方で、行動や工夫、取り組む姿勢は、子どもが自ら選び取ったものであり、そこを認められることで自信とやる気が育まれます。
また、「褒める」ことが目的化してしまうと、子どもは大人の評価を得るために動くようになり、自発性が失われてしまう危険性もあります。
声かけの本質は、評価ではなく“理解”と“共感”です。
子どもの努力や考え方を丁寧にすくい上げることで、内側から湧き出るモチベーションを支えることができます。
「結果」より「プロセス」を認める声かけ
多くの場面で、子どもは「できたか、できなかったか」で評価されがちです。
しかし、その過程でどれだけ悩み、工夫し、挑戦したかというプロセスは、成長の核になる部分です。
そこに目を向けて言葉をかけることが、やる気と自己効力感を高める第一歩となります。
たとえば、テストの点数が思うように取れなかったときでも、「わからなかったところを自分で調べたのはすごいね」「最後まで諦めなかった姿勢が立派だったよ」と伝えることで、行動の価値が肯定されます。
これにより、子どもは「やってよかった」「また挑戦したい」という感覚を持つようになります。
プロセスを認める声かけは、結果の良し悪しによって気分が左右される不安定な状態から、努力すること自体を価値あるものと感じる安定した自己認識へと導いてくれます。
結果は一時的な達成でも、プロセスに注目すれば継続的な成長につながるのです。
自己肯定感を育む“具体的な褒め方”の工夫
漠然とした褒め言葉は、子どもにとって手応えのないものになりがちです。
「えらいね」「すごいね」だけでは、自分のどこが良かったのかがわからず、やる気や成長への意識につながりにくくなります。
そのため、褒める際には「何に対して」「どう感じたか」を具体的に伝えることが重要です。
「最後まで静かに話を聞けていたから、先生も安心して授業ができたよ」「前より字が丁寧になっていて読みやすくなったね」といったように、具体性を持たせることで、子ども自身が自分の行動と評価の関係を理解できるようになります。
また、結果ではなく姿勢や工夫に焦点を当てることで、子どもは「自分は価値ある存在なんだ」と感じるようになります。
これが自己肯定感を育む土台となり、次のチャレンジにも前向きに取り組めるようになるのです。
褒めることは、ただ持ち上げるのではなく、子どもの成長の「どこ」に大人が注目しているかを伝える行為です。
その積み重ねが、子どものやる気と才能を引き出す確かな力になります。
個性や才能を引き出す声かけの工夫

すべての子どもが、同じ方法でやる気を高め、才能を伸ばせるわけではありません。
それぞれに異なる性格や特性、興味関心があり、その違いこそが個性の源であり、可能性の入口です。
そのため、効果的な言葉かけには「正解」はなく、「相手に合った表現」を模索する姿勢が求められます。
教育現場でも家庭でも、つい他の子と比較したり、平均的な成長を基準にした声かけをしがちです。
しかし、それでは子ども自身が持っている潜在的な力や創造性にふたをしてしまうことになりかねません。
重要なのは、その子自身がどんな特性を持っているか、どこに興味を持ち、どんな表現を好むのかを日常のやりとりの中で観察し、理解することです。
相手の視点に立つことで、伝えるべき言葉の内容も、語調も変わります。
静かな性格の子には、安心感を与える柔らかい表現が効果的であり、エネルギーにあふれた子には挑戦を後押しするような言葉が響く場合もあります。
声かけは単なる習慣ではなく、子ども一人ひとりと丁寧に向き合うための“関係づくりの技術”とも言えるでしょう。
子どもの特性に合わせた言葉の選び方
発達の段階や性格によって、響く言葉は大きく異なります。
細かなことに気がつく子どもには、行動の中の変化や努力を具体的に言語化して伝えると、自分を認めてもらえたという実感につながります。
反対に、感情の起伏が大きい子には、安心感や信頼を前提とした一言が、次の行動を支える力になります。
また、子どもの関心の方向性にも注目が必要です。
興味を示している対象や話題に対して、肯定的に応答し、それに付け加えるような声かけをすることで、子どもの意欲と集中力が引き出されやすくなります。
一律の言い回しではなく、その子の言動をよく観察し、「何を見て」「どう感じているか」を推測する姿勢を持つことで、言葉は単なる伝達手段から、信頼を深める道具へと変わります。
関係性の中で磨かれる言葉の選び方こそ、子どもの個性を尊重し、伸ばす鍵となります。
「苦手」を「可能性」に変える声かけの視点
子どもは日々、さまざまな壁に直面します。
できないこと、うまくいかないことに対して、大人がどのような言葉をかけるかは、その子の「自己認識のかたち」に直結します。
不得意な領域に対して否定的な言葉を浴びせられると、自分の能力を狭く捉えるようになり、新しい挑戦を避ける傾向が強まります。
しかし、苦手なことの中にも、その子なりの可能性が隠れている場合があります。
たとえば、作業に時間がかかる子には「ていねいに取り組む力がある」と伝えることで、苦手意識をポジティブに転換できます。
目立ちにくい長所や努力の姿勢に焦点を当てることで、子ども自身が自分の中にある価値を認識できるようになります。
ネガティブな状況を、成長の材料として扱う視点があるかどうか。
それが、才能を引き出す声かけの質を左右します。
大人の一言が、子どもの世界の見え方を変え、自信と好奇心を取り戻すきっかけになるのです。
家庭や教育現場で実践できる言葉かけの事例集

理論や考え方がわかっていても、いざ子どもと向き合ったときにどんな言葉をかければよいか迷う場面は多くあります。
言葉かけは感情と直結しているからこそ、つい反射的に出てしまうこともありますが、あらかじめ「こういう場面ではこう伝えてみよう」と準備しておくことで、子どもの反応や関係性に大きな変化が生まれます。
このセクションでは、家庭や教育の現場で日常的に使いやすく、なおかつ子どものやる気や自信を育てる実践的な言葉かけを紹介します。
特別なスキルや環境がなくても、少しの意識と工夫で日常の会話が変わり、子どもの行動や表情にも変化が現れていきます。
家庭で使える“やる気スイッチ”の言葉
家庭は、子どもにとって最も安心できる場所であり、同時に最も素の自分が出せる場所です。
そのため、日常の声かけが子どもの内面に深く届きやすく、やる気や自己肯定感の土台になります。
たとえば、準備や片づけに時間がかかる子には、「自分のペースでいいから、やろうとしているのが伝わってきたよ」といった一言がプレッシャーを和らげつつ行動を促します。
言われたからやるのではなく、自分でやってみようと思えるような声かけを意識することで、自発的な行動が増えていきます。
また、「今日のここがよかったな」と、一日の終わりに短く伝える習慣は、安心感と自信を育てるのに非常に有効です。
特別な出来事でなくても、気づきや小さな変化に注目する姿勢が、子どもに「自分は見てもらえている」という感覚を与えます。
家庭での声かけは、一つひとつが積み重なっていく関係性の基礎です。
日々の何気ない一言が、やる気を支える力になります。
保育・教育現場での具体的な声かけ実践例
集団生活の中で子どもと関わる保育士や教員にとっても、言葉かけの質は教育の根幹に関わる要素です。
特に未就学児や小学校低学年では、言葉一つで行動が変わるだけでなく、その後の学習姿勢や人間関係の築き方にも影響を与えます。
集団活動中に集中できない子どもには、行動を叱る前に「○○をしてくれると、みんなも助かるよ」と伝えることで、責任感と役割意識が育まれます。
周囲との関係の中で行動の意味を実感できると、協力することの意義を自然に学べます。
また、課題に取り組む際には「この前よりスムーズにできていたね」「工夫したところに気づいたよ」と伝えることで、子ども自身が成長を実感しやすくなります。
評価ではなく観察を伝えることで、子どもとの信頼関係が深まり、次への挑戦を後押しする力になります。
教育現場では、多様な子どもたちに対して一律の対応が求められることもありますが、その中でも「一人ひとりを見ている」という視点を言葉で届けることが、心の距離を縮める鍵となります。
正解を与えるのではなく、可能性を信じて言葉をかけることが、教育者にできる最大のサポートです。
まとめ|言葉の力で、子どものやる気と才能を育てよう

子どものやる気や才能は、生まれつき決まっているものではなく、大人の関わり方によって大きく変化していくものです。特に、日々の言葉かけはその子の自己認識や行動の動機づけに直接影響するため、教育の中でも非常に重要な要素といえます。
本記事では、「結果よりもプロセスを認めること」「個性に合わせた声かけを心がけること」「苦手な部分にも可能性を見出す視点を持つこと」など、保護者や教育者が意識したい基本的な考え方を紹介してきました。さらに、家庭や教育現場での実践例を通じて、明日からすぐに活かせる言葉かけの工夫もご提案しました。
どんなに素晴らしい能力も、自分でその価値に気づけなければ十分に発揮されません。大人の声かけは、子どもにとっての「鏡」であり、「道しるべ」です。日々の関わりの中で、安心感や達成感、挑戦する楽しさを感じられるような言葉を届けることが、子どもたちの成長にとって何よりの支えとなります。
子どもの未来を信じ、可能性を引き出す言葉をかける。それは、教育に関わるすべての大人にできる、小さくて大きな贈り物です。
今日のひと声が、明日のやる気と才能の芽を育てていく――そんな想いを胸に、子どもと向き合う時間を積み重ねていきましょう。