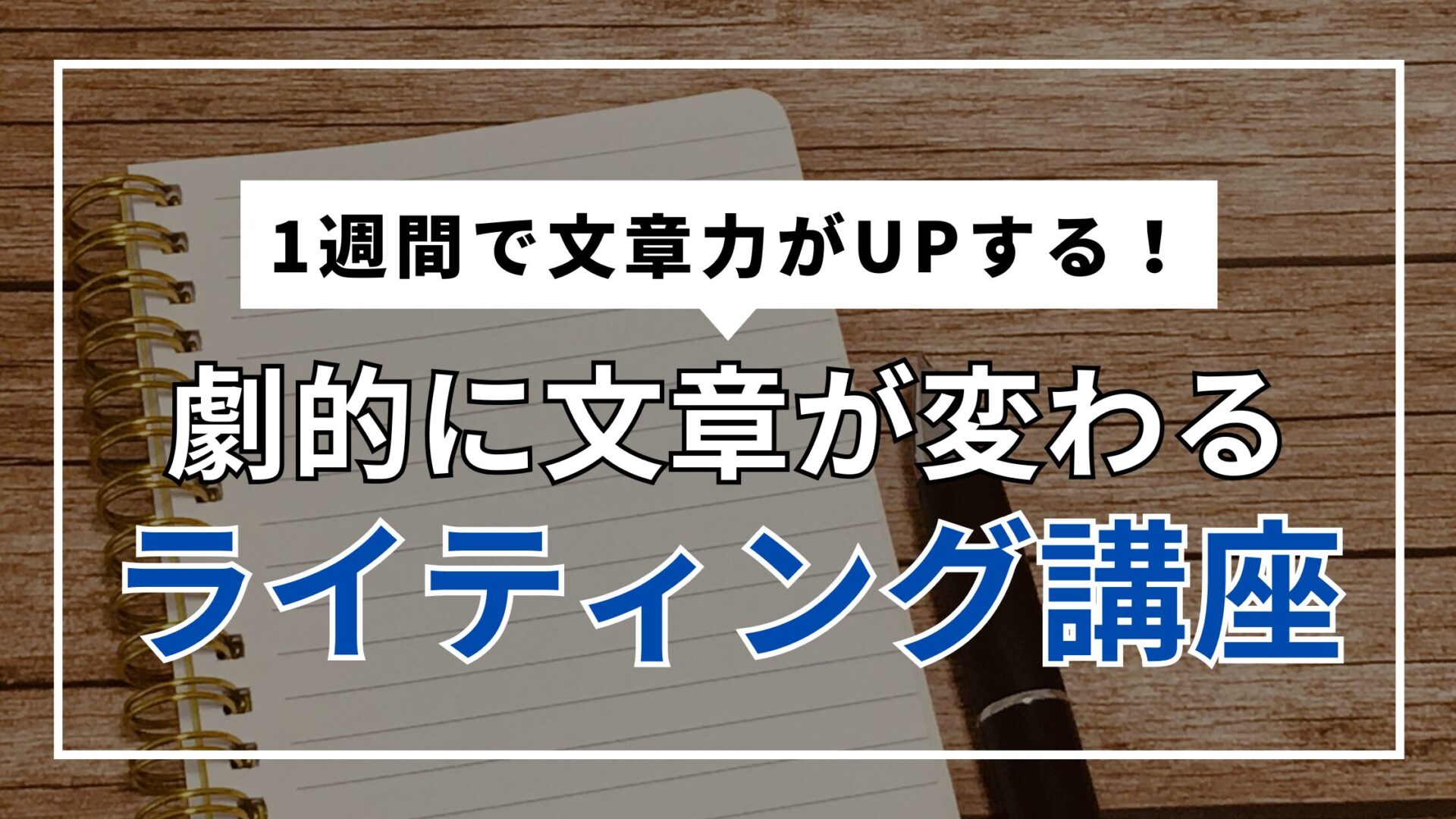はじめに|「文章が書けない」を解決するライティングスキルUP術
「いざ文章を書こうと思っても、うまくまとまらない…」
「何を書けばいいのかわからず、手が止まってしまう…」
「自分の書いた文章が読みにくいと感じる…」
このような悩みを抱えている人は多いですが、安心してください。ライティングは「センス」ではなく「スキル」です。
つまり、適切な方法を学び、練習を重ねれば、誰でも上達できます。
近年では、ビジネスシーンだけでなく、SNSやブログ、メール、企画書など、さまざまな場面で「伝わる文章を書く力」が求められています。特に、情報が溢れる時代において、「短時間で、的確に、わかりやすく伝えるスキル」は非常に重要です。
では、ライティング初心者が文章を劇的に改善するには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか?
この記事では、文章の基本構成から、具体的な書き方のコツ、効果的な練習方法まで、ライティングスキルを向上させるための実践的なノウハウを解説します。
文章を書くのが苦手な人の多くは、以下のような課題を抱えています。

「文章が書けない」と感じる理由とは?
- 何を書けばいいのかわからない → 文章のテーマや構成を考えずに書き始めると、途中で行き詰まる
- 読みにくい文章になってしまう → 1文が長すぎたり、話の流れが整理されていない
- 表現が曖昧で伝わらない → 具体性がなく、読み手に意図が正しく伝わらない
- 文章の推敲・修正の仕方がわからない → 書いた後にどう直せば良いかわからない
これらの問題を解決するには、「文章の基本ルールを知ること」と「適切なトレーニングをすること」が不可欠です。
ライティングスキルを上げるための3ステップ
ライティングの上達には、次の3つのステップが重要です。
- 書く力を鍛える
→ 具体的なトレーニング法を実践し、実際に文章を書く習慣をつける - 改善する力をつける
→ 推敲(すいこう)の方法を学び、より伝わりやすい文章に仕上げる - 基本を押さえる
→ 文章の「型」を理解し、シンプルでわかりやすい文章を書く
ライティングは「書きながら上達するスキル」です。最初から完璧を目指すのではなく、コツを理解しながら少しずつ文章を書き、改善していくことが大切です。
この記事で学べること
本記事では、以下のポイントを詳しく解説します。
- ライティング初心者がまず押さえるべき基本
→ 「文章を書く前に意識すべきポイント」と「伝わる文章の型」 - 文章が劇的に読みやすくなる書き方のコツ
→ 「シンプルな表現の使い方」と「読者の興味を引く構成」 - ライティングスキルを上達させる練習法
→ 「文章力を鍛えるトレーニング」と「おすすめの勉強法」 - よくあるミスを避けて文章の質をアップする方法
→ 「初心者が陥りがちなNGパターン」と「推敲テクニック」
文章がうまく書けないのは、「才能」ではなく「練習と知識が不足しているだけ」です。コツをつかめば、確実に上達できます。本記事を参考に、ライティングスキルを劇的に向上させましょう!
目次
ライティング初心者がまず押さえるべき基本
ライティングを上達させるには、まず 「基本の型」を理解することが重要です。
文章は感覚で書くものではなく、一定のルールや構成に従うことで、読みやすく伝わりやすい文章になります。初心者が最初に意識すべきポイントを押さえておきましょう。

文章を書く前に意識すべきポイント
文章を書く際に、「いきなり書き始める」と途中で詰まってしまうことがよくあります。ライティングの効率を上げるために、以下のポイントを意識しましょう。
1. 「誰に向けた文章か?」を明確にする
文章は「誰に読んでもらうのか」を決めてから書くことが大切です。例えば、初心者向けの記事と、上級者向けの記事では、使う言葉や説明の仕方が変わります。
- ターゲットを決める:「初心者?ビジネスパーソン?学生?」
- 読者の悩みを整理する:「どんな問題を解決したいのか?」
- 適切な語彙を選ぶ:「難しい言葉は避けた方がよいか?」
2. 文章の目的を明確にする
記事やブログを書く際は、「読者に何を伝えたいのか?」を意識しましょう。以下のような目的を明確にすると、文章の方向性が定まりやすくなります。
- 情報を伝える:「ライティングの基本を知ってもらう」
- 行動を促す:「この記事を読んで、実際に文章を書いてもらう」
- 共感を得る:「ライティング初心者の悩みに寄り添う」
3. 事前に「構成」を考える
構成を決めずに文章を書くと、話がまとまらずに読みにくくなります。基本の「型」を意識して、書くべき内容を事前に整理しましょう。
おすすめの構成は「PREP法」です。
PREP法の基本構成
- Point(結論):「文章がうまく書けないのは、基本の型を知らないからです」
- Reason(理由):「構成が決まっていないと、読みにくい文章になりやすいです」
- Example(具体例):「例えば、PREP法を使うと、簡潔で分かりやすい文章になります」
- Point(再結論):「文章を書く前に、PREP法で構成を決めましょう」
このように 「結論→理由→具体例→結論」 の流れで書くと、読み手が理解しやすい文章になります。

伝わる文章の基本構成(PREP法・結論ファースト)
文章のわかりやすさを決めるのは「構成の良し悪し」です。
初心者でも簡単に使える「結論ファースト」の型を活用し、読者に伝わりやすい文章を書きましょう。
1. PREP法を活用する
前述したPREP法は、論理的で読みやすい文章を書くための基本テクニックです。特にブログ記事やビジネス文章では、多くのライターが活用しています。
例:「ライティングスキルを上げるには?」
- 結論(Point):「ライティングスキルを上げるには、まず基本の型を学ぶことが重要です」
- 理由(Reason):「文章の型を知らないと、読みにくく伝わりにくい文章になってしまうからです」
- 具体例(Example):「例えば、PREP法を活用すると、文章の構成が明確になります」
- 再結論(Point):「文章を書く前に、PREP法の流れを意識するだけで、劇的に読みやすい文章になります」
このように、「結論から述べる」ことで、読者が迷わずスムーズに理解できます。
2. 「結論ファースト」で書く
特にWebライティングでは、結論を先に伝えることが鉄則です。読者は忙しく、文章をじっくり読む時間がないため、最初に要点を伝えましょう。
NG例:「ライティングを上達させるには、いくつかの方法があります。まず、基本を学ぶことが大切です。例えば…」
OK例:「ライティング上達の第一歩は、基本の型を学ぶことです。例えば、PREP法を使うと…」
このように、最初に結論を述べることで、読者が興味を持ちやすくなります。
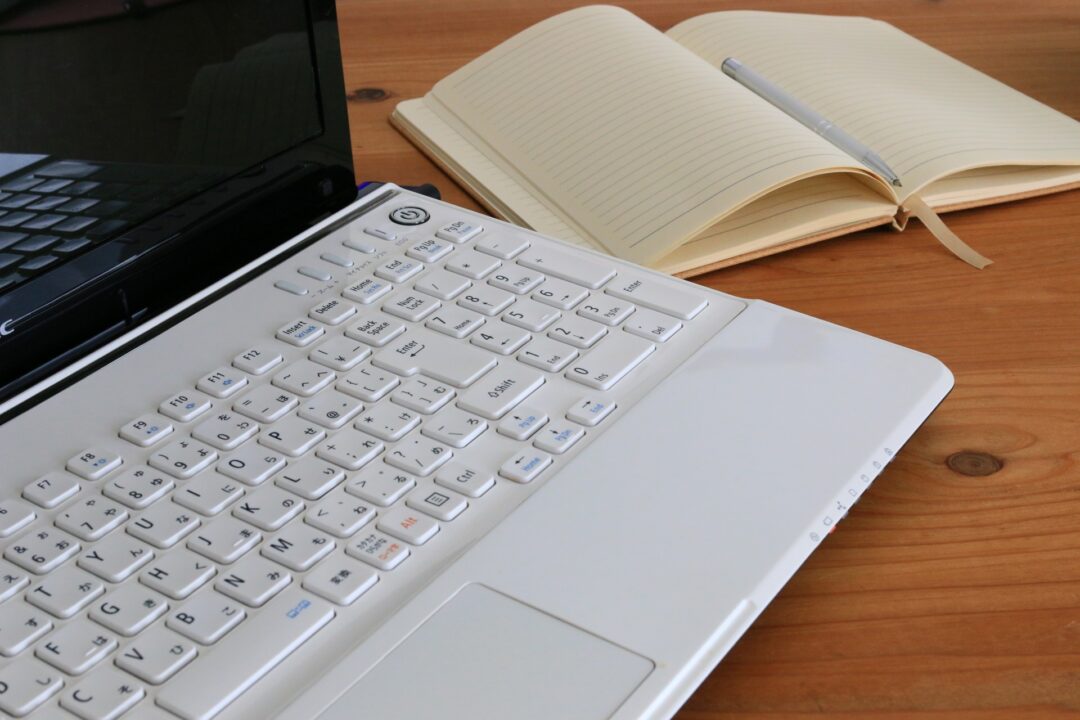
文章が劇的に読みやすくなる書き方のコツ
ライティング初心者の多くが抱える悩みの一つに、「自分の書いた文章が読みにくい」という問題があります。文章がスムーズに読めないと、読者は途中で離脱してしまい、伝えたいことが伝わりません。
そこで、この章では 「シンプルで分かりやすい表現を使う方法」と「読者の興味を引く文章の組み立て方について解説します。
シンプルで分かりやすい表現を使う方法
文章が読みにくい原因の多くは「無駄な表現」や「曖昧な言葉」にあるため、できるだけシンプルな表現を心がけることが大切です。以下のポイントを押さえて、読みやすい文章を書く習慣をつけましょう。
1. 一文を短くする
初心者がよくやってしまうミスの一つが、「一文が長すぎること」です。一つの文にいくつもの情報を詰め込むと、読者が内容を理解しにくくなります。
NG例:「私は最近、ライティングスキルを向上させたいと思い、様々な本を読んで勉強しているのですが、なかなか実践に落とし込むことができずに困っています」
OK例:「私は最近、ライティングスキルを向上させたいと考えています。そのために本を読んで勉強していますが、実践に落とし込むのが難しく感じています」
目安として「1文は40〜60字以内」にまとめると、格段に読みやすくなります。
2. 余計な言葉を削る
「なくても意味が通じる言葉」は、できるだけ削りましょう。不要な言葉があると、文章が冗長になり、読者の負担が増えてしまいます。
NG例:「とても大切なことをお伝えしたいと思いますが、簡単に説明すると…」
OK例:「大切なことを簡単に説明します」
無駄な表現を省くことで、スッキリとした文章になります。
3. 専門用語や難しい言葉を避ける
初心者向けの記事を書く場合、専門用語や難解な表現はできるだけ避けるのが鉄則です。読者の理解度を考えながら、誰でもわかる表現を使いましょう。
NG例:「本稿では、文章構成の最適化に寄与するプラクティスについて言及する」
OK例:「この記事では、文章をわかりやすくする方法を解説します」

読者の興味を引く文章の組み立て方
文章を書く際には、「読者を引き込む構成」を意識することが重要です。以下のテクニックを活用すれば、最後まで読んでもらえる文章になります。
1. 「最初の一文」で読者の関心をつかむ
読者は、最初の数秒で「この文章を読む価値があるかどうか」を判断します。そのため、最初の一文で興味を引くことが重要です。
NG例:「ライティングは文章を書く技術のことです」
OK例:「あなたは、文章を書こうとして手が止まったことはありませんか?」
疑問形やインパクトのある言葉を使うことで、読者の興味を引きやすくなります。
2. 「結論→理由→具体例→再結論」の流れを意識する
読者が理解しやすい文章にするためには、「結論ファースト」の型を活用しましょう。
PREP法の流れ
- 結論(Point):「文章をわかりやすくするには、短く簡潔に書くことが重要です」
- 理由(Reason):「長すぎる文章は、読者が理解しにくくなるからです」
- 具体例(Example):「例えば、1文を60字以内にすると、読みやすさが格段に向上します」
- 再結論(Point):「文章を短くするだけで、伝わりやすさがアップします」
この流れを意識すると、簡潔で論理的な文章を書けるようになります。
3. 読者が「次を読みたくなる仕掛け」を作る
文章を最後まで読んでもらうためには、「続きが気になる仕掛け」を作ることが重要です。
- 次の章へ誘導する:「では、具体的にどのようにライティングスキルを向上させればいいのでしょうか?次の章で詳しく解説します」
- 疑問を投げかける:「あなたの文章は、読者に伝わっていますか?」
- ストーリーや事例を交える:「実際に、プロのライターがどのように文章を改善しているのか見てみましょう」
このように、「次を読みたい」と思わせる工夫をすると、読者の離脱を防ぐことができます。
ライティングスキルを上達させる練習法
文章をスムーズに書けるようになるためには、「書く」だけでなく「学ぶ」「直す」ことも重要です。ライティングは、実践を積めば確実に上達するスキルなので、適切な練習方法を取り入れることで、短期間でも文章力が向上します。
この章では、文章力を鍛えるトレーニング方法と良い文章を学ぶためのおすすめ勉強法を紹介します
文章力を鍛えるトレーニング方法
ライティングを上達させるには、継続的な練習が必要です。ここでは、効果的なトレーニング方法をいくつか紹介します。
1. 「毎日100文字ライティング」を続ける
ライティング初心者の方は、まず「短い文章を書く習慣」をつけることが大切です。いきなり長文を書くのではなく、1日100文字程度の簡単な文章を書くことから始めましょう。
このように、無駄な言葉を削ぎ落とし、簡潔に書く練習をすると、文章の密度が高くなります。
2. 「写経ライティング」でプロの文章を真似る
文章力を向上させるためには、良い文章にたくさん触れることが大切です。特に、プロのライターや作家の文章を「手書き」または「タイピング」で写す」 ことで、文章のリズムや構成を自然と身につけられます。
写経ライティングのやり方
- お手本となる文章を選ぶ(新聞、コラム、ブログ記事など)
- その文章をそのまま書き写す(できれば声に出しながら書く)
- なぜこの表現が使われているのかを分析する
写経を続けると、「プロがどのように言葉を選び、どのような流れで書いているのか」が理解できるようになります。
3. 「3行要約」で要点をまとめる力を鍛える
文章を分かりやすく書くためには、「本質を抜き出して要約するスキル」 が必要です。
3行要約トレーニング
- 新聞記事やブログ記事を1つ選ぶ
- その内容を3行にまとめる(100〜150文字以内)
- 自分の言葉で要約し、元の文章と比較する
要約力を鍛えることで、「余計な表現を減らし、シンプルに伝える力」が身につきます。
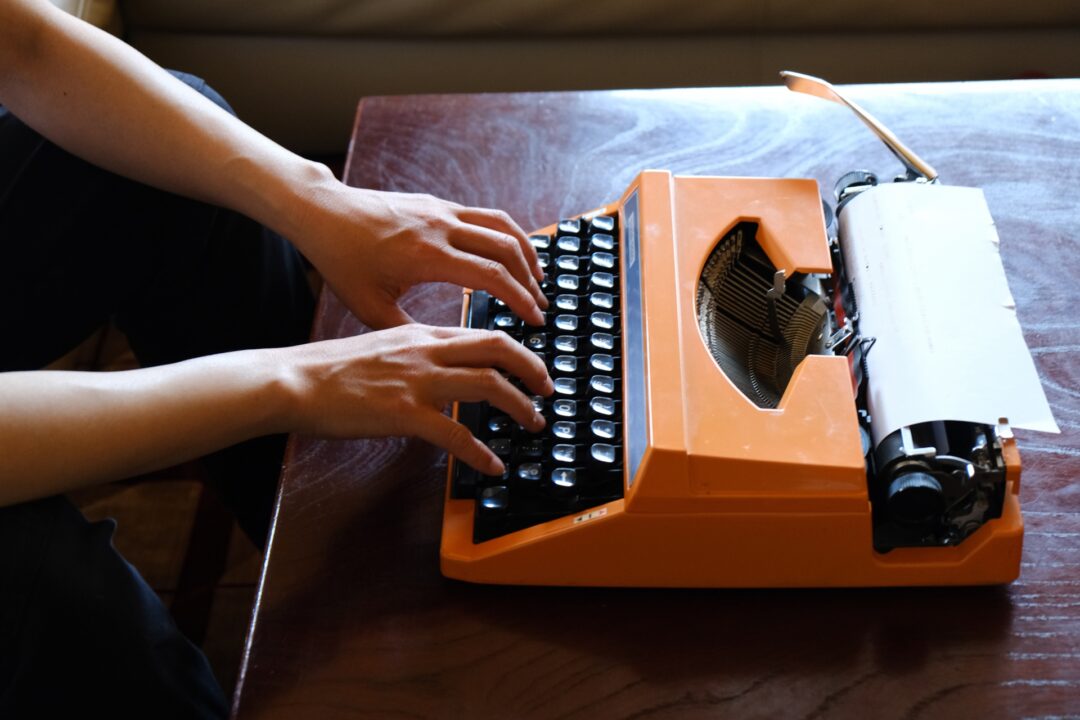
良い文章を学ぶためのおすすめ勉強法
文章力を向上させるには、良い文章を「読む」「分析する」「書く」の3ステップが重要です。
1. 「良い文章」をたくさん読む
良い文章に触れることで、自然とライティングのスキルが向上します。初心者におすすめの本を紹介します。
本を読む際は、「なぜこの文章は読みやすいのか?」と考えながら読むと、より効果的です。
2. 「構成」を意識して分析する
文章をただ読むのではなく、「どのような構成で書かれているのか?」 を意識すると、ライティングのスキルが飛躍的に向上します。
構成を分析するポイント
- 導入部分 → どうやって読者の興味を引いているか?
- 本題 → どのように情報が整理されているか?
- まとめ → どのように結論へつなげているか?
記事を分解して考えることで、「論理的な文章の流れ」を学ぶことができます。
3. 書いた文章を「他人に読んでもらう」
自分では「わかりやすい」と思っていても、実際に読者に伝わっているとは限りません。他人に読んでもらうことで、「どこが分かりにくいのか?」を客観的に判断できます。
フィードバックをもらう方法
✅ SNSで投稿して反応を見る
✅ 友人や家族に読んでもらう
✅ オンラインコミュニティやブログで公開する
読者の意見を取り入れながら改善することで、より伝わる文章を書けるようになります。

まとめ|ライティングスキルを上達させるには?
文章力を鍛えるトレーニング
- 「毎日100文字ライティング」で短くまとめる力をつける
- 「写経ライティング」でプロの表現を学ぶ
- 「3行要約」で要点をまとめる練習をする
良い文章を学ぶための勉強法
- おすすめの本を読む(構成を意識しながら)
- 良い文章の分析をする(なぜ読みやすいのか考える)
- 他人に読んでもらい、フィードバックを受ける
ライティングスキルは、一朝一夕で身につくものではありませんが、毎日の習慣を積み重ねることで確実に向上します。

よくあるミスを避けて文章の質をアップする方法
ライティング初心者が文章を書く際、意識せずにやってしまいがちな「ミス」があります。どれだけ練習を重ねても、間違った書き方を続けていると、文章の質は向上しません。
この章では、初心者が陥りがちな文章のNGパターンと読みやすい文章にするための推敲テクニックを紹介します。ミスを避け、文章の質を劇的にアップさせましょう!
初心者が陥りがちな文章のNGパターン
文章を読みにくくする原因の多くは、「無意識のうちにやっているミス」です。以下のポイントに気をつけるだけで、文章がぐっと読みやすくなります。
1. 一文が長すぎる
「伝えたいことがたくさんあるから」と、1つの文にいくつもの情報を詰め込んでしまうのはNGです。一文が長くなると、読者が途中で迷子になり、伝わりにくい文章になってしまいます。
NG例:「私は昨日、友人とカフェに行き、コーヒーを飲みながら仕事の話をして、その後映画を見てから帰宅しました」
OK例:「昨日は友人とカフェへ行き、コーヒーを飲みながら仕事の話をしました。その後、映画を見て帰宅しました」
一文は40〜60字以内に収めるように意識しましょう。
2. 主語と述語の関係が曖昧
「誰が」「何をしたのか」がはっきりしないと、読者に誤解を与えたり、伝わりにくい文章になります。
NG例:「この本を読んで、文章の大切さがわかりました」(誰がわかったのか不明)
OK例:「私はこの本を読んで、文章の大切さを理解しました」
主語と述語の対応を正しくすることを意識しましょう。
3. 抽象的な表現が多い
「すごい」「いい感じ」「いろいろ」など、曖昧な表現を多用すると、読者に具体的なイメージが伝わりません。
NG例:「この映画はすごくよかったです」
OK例:「この映画は、ストーリーの展開が予想外で驚きました。特に、ラストシーンの演出が秀逸でした」
「具体的にどうすごいのか?」を意識して書くことで、読者の理解が深まります。
4. 接続詞の使いすぎ
「そして」「しかし」「つまり」などの接続詞を多用しすぎると、文章が不自然になり、くどい印象を与えます。
NG例:「私はコーヒーが好きです。しかし、紅茶も好きです。そして、ジュースも飲みます」
OK例:「私はコーヒーが好きですが、紅茶やジュースもよく飲みます」
接続詞は必要な部分だけ使うように意識しましょう。

読みやすい文章にするための推敲テクニック
文章を書いたら、そのまま公開するのではなく、「推敲(すいこう)」をすることで、より洗練された文章に仕上げることができます。
1. 「音読」して違和感をチェックする
自分の書いた文章を「声に出して読む」と、リズムの悪い部分や不自然な表現に気づきやすくなります。
読みにくいと感じた部分は、短くしたり、言い換えたりして調整しましょう。
2. 「主語と述語」を確認する
文章を書いた後で、「主語」と「述語」の対応関係をチェックすることで、誤解を招く文章を防げます。
NG例:「友人は『この商品を使うと、肌の調子が良くなる』と言っていました」
OK例:「友人は『この商品を使うと、肌の調子が良くなる』と言っていました」
読者が正しく理解できるように、文の構造を見直しましょう。
3. 「冗長な表現」を削る
文章の意味が変わらない不要な部分は、できるだけ削ることで、スッキリとした文章になります。
NG例:「この映画はとても素晴らしく、特に最後のシーンが本当に感動的でした」
OK例:「この映画のラストシーンは感動的だった」
できるだけ「短く・簡潔に」書くことを意識しましょう。
4. 「視点」を統一する
文章の途中で「一人称」「三人称」などの視点が変わると、読者が混乱してしまいます。
NG例:「私はこの本を読んで学んだことを紹介します。その本を読むと、あなたも勉強になるでしょう」(「私」と「あなた」が混在)
OK例:「私はこの本を読んで学んだことを紹介します。この本を読むことで、読者も新たな発見があるはずです」
文章全体の視点を統一することで、読みやすさが向上します。

まとめ|ミスを防いで文章の質をアップしよう
文章のクオリティは、「書いた後にどれだけ修正を加えられるか」で決まります。推敲を習慣にすることで、自然と文章力が向上します。
これで、ライティング初心者が「文章を書きやすくするコツ」と「文章の質を高める方法」を学ぶことができました。
この記事で紹介した内容を実践し、少しずつライティングスキルを向上させていきましょう!