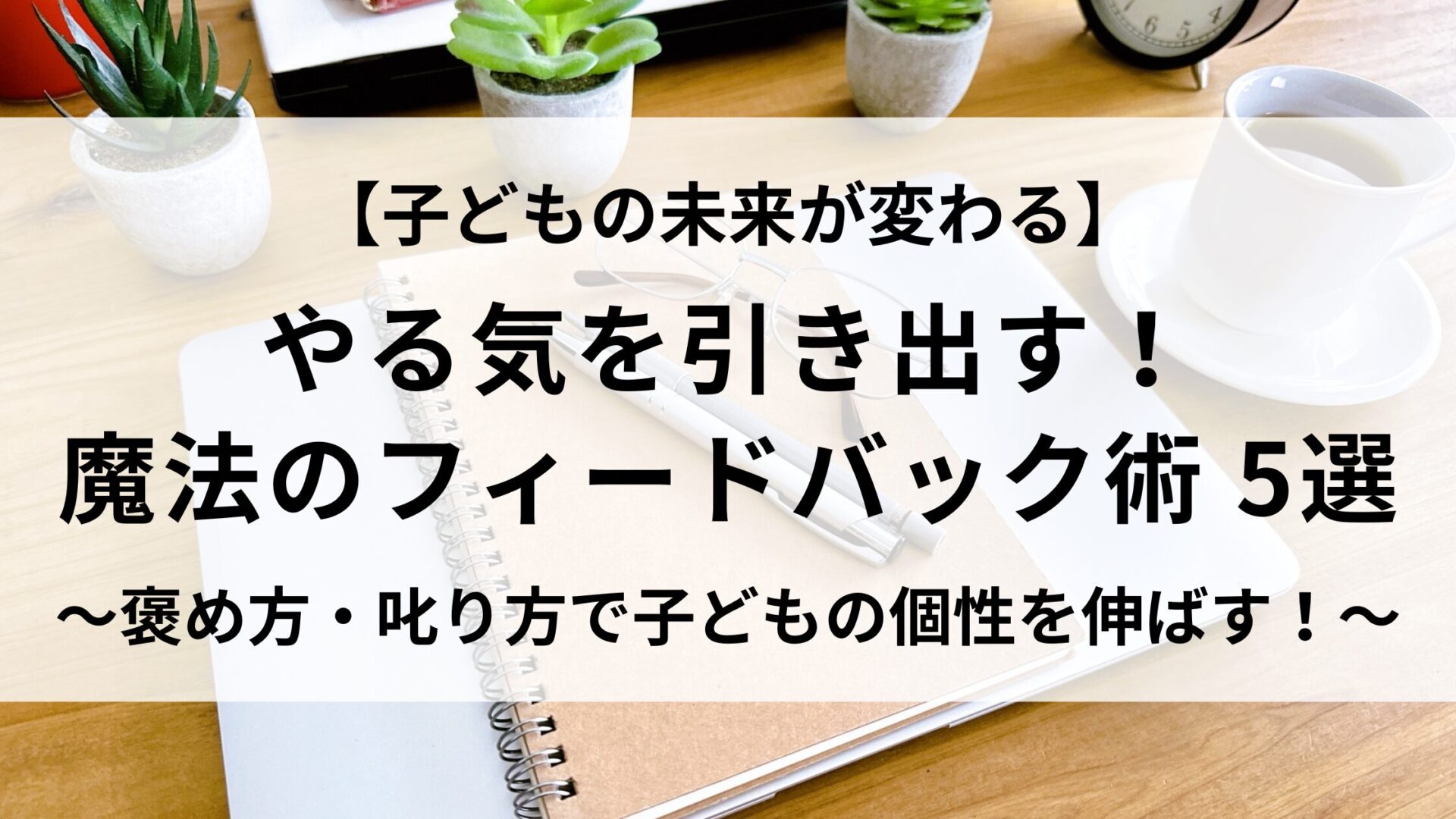はじめに
子どもが持つ才能を最大限に伸ばすためには、日々の接し方や声かけ、つまりフィードバックの質が大きく影響します。
近年の教育研究でも、「フィードバックは学習と成長を促す最も効果的な手段のひとつ」と位置づけられており、親や教育者がどのような言葉を使うかが、子どものやる気や自己肯定感、さらにはその子の人生にまで影響を及ぼすとされています。
たとえば同じ褒め方でも、「すごいね」と伝えるだけで終わるのか、「どの部分がよかったか」を具体的に伝えるのかで、子どもの受け取り方は大きく異なります。
才能とは、生まれつき決まっているものではありません。
適切なフィードバックによって、眠っていた可能性が引き出され、自分でも気づかなかった力が育まれていくのです。
とくに近年注目されているのが「成長マインドセット」という考え方です。
これは、能力や知識は努力や学習を通じて伸ばせるという認識であり、子どもにこの考えを持たせるためには、周囲の大人による指導とフィードバックが欠かせません。
そのためには、漠然と褒めるのではなく、子どもの行動や工夫に目を向けた具体的な声かけが必要です。
本記事では、子どもの個性に応じたフィードバックの方法や、親・保育士・教員など教育に関わる方が実践しやすい具体的なコーチング手法について解説します。さらに、やる気を引き出す褒め方のポイントや、成長を促す日常の声かけの工夫など、家庭や教育現場ですぐに使える内容もご紹介します。
・どう接すれば、もっとこの子の才能を伸ばせるのだろう
・どんなフィードバックが効果的なのか知りたい
と感じている方にとって、本記事が日々の教育や子育てに役立つヒントとなれば幸いです。
目次
子どもの才能を引き出すには? 今注目される「フィードバック」の力
「子どもには誰にでも伸びる可能性がある」
この考え方は、教育心理学や脳科学の進展とともに、今や多くの親や教育者にとって常識になりつつあります。
しかし、その可能性をどのように引き出すかという問いに対する答えは、意外と見過ごされがちです。
鍵となるのは、子どもへの日常的なフィードバックです。
フィードバックとは、子どもの行動や思考に対して返す言葉や態度のことで、単なる褒め言葉や注意だけではありません。
教育の現場では近年、「フィードバックは“情報”であるべき」という考え方が重視されており、評価ではなく、次の行動に活かせる具体的な情報を伝えることが大切だとされています。
たとえば、「がんばったね」ではなく「最後まで集中して取り組んでいたね」と伝えることで、子どもは「自分のどんな行動が評価されたのか」を理解し、再現しようとします。こうしたやりとりを重ねることで、自信ややる気、そして自己肯定感が育っていくのです。
また、子どもの才能は、生まれつきの能力だけで決まるわけではありません。
心理学者キャロル・ドゥエックの研究では、「才能や知能は努力と工夫で伸びる」と考える子どもほど、困難に立ち向かい、学習や成長を楽しむ傾向があることが明らかになっています。
そしてその思考スタイルを支えるのが、周囲の大人によるポジティブで建設的なフィードバックです。
つまり、親や先生の言葉は、子どもの才能の種に光を与える存在だと言えます。
声かけひとつで、子どもは自分の可能性を信じ、自発的に挑戦し始める!
才能は「見つける」より「育てる」もの
「この子には才能がある」「才能がないかもしれない」といった言葉を耳にすることがありますが、才能とは発見するものではなく、育てていくものという考え方が、現代の教育では主流になりつつあります。
確かに、生まれつき得意なことや好きなことは子どもによって異なりますが、それが目に見える形で花開くかどうかは、環境とフィードバックの影響が大きいのです。
最初は絵を描くのが少しうまいだけだった子でも、「色の使い方が面白いね」「この表現は君にしかできないよ」といった具体的なフィードバックを繰り返すことで、「自分は絵が得意なんだ」と自信を持ち、さらに描く意欲を育んでいきます。
これがまさに才能を育てるというプロセスです。
大人が「この子は何が得意か」だけを探そうとする
「どのような行動や工夫を伸ばしてあげるか」という視点を持つ
そのためには、結果ではなく過程に注目し、「どう取り組んだか」を丁寧に見て、子どもに伝えることが必要です。
才能の芽は、小さな積み重ねによってゆっくりと育ちます。
それは、特別な習い事や特化した教育ではなく、日常の中の何気ない一言、ちょっとした励まし、挑戦への背中押しから始まるのです。
なぜ今、教育においてフィードバックが重要なのか
これまでの教育では、「できた」「できなかった」といった結果中心の評価が主流でした。
しかし現在は、その過程に注目し、子どもが次の行動に活かせる情報を与えるフィードバックの重要性が高まっています。
これは、子どもの自立的な学びを促し、長期的な成長を支えるために不可欠なアプローチです。
近年の研究では、フィードバックが子どものやる気や学習意欲に与える影響は非常に大きいことが明らかになっています。
単に「よくできたね」と褒めるだけでは、子どもはその理由を理解できず、再現性のある行動につながりません。
一方、「前回より工夫して取り組んでいたね」と伝えると、どこを伸ばせばよいのかが明確になり、学びへの自信が生まれます。
特に、テストの点数や結果にばかり注目してしまうと、子どもは「できなかった自分」にばかり目がいき、挑戦を避けるようになります。しかし、挑戦したこと自体を認めるフィードバックを受けると、失敗も学びの一部と捉えられるようになり、継続的な成長につながっていきます。
フィードバックは単なる評価ではなく、子どもとの対話の手段として位置づけることが重要!
大人がどう言葉をかけるかによって、子どもの受け取り方や将来への姿勢が変わってくるのです。
やる気と自己肯定感を育てるフィードバックの基本
子どもが自ら学び、挑戦し、成長していくためには、
・やる気
・自己肯定感
の土台が欠かせません。
そして、この2つを支える大きな要素が、日常の中でのフィードバックです。
大人からの言葉が、子どもの心にどう響くか。その積み重ねが、やる気と「自分はできる」という感覚を少しずつ育てていきます。
自己肯定感とは、「自分は大切な存在だ」と感じられる力です。
これは甘やかすこととは異なり、努力や工夫、成長の過程を認める声かけによって強化されていきます。
「すごいね」「えらいね」といった一言
「こんなふうに考えて工夫したんだね」と、行動の中身に着目した言葉
こういった言葉をかけることで、子どもは自分の取り組みを客観的に捉えることができるようになります。
また、やる気には「内発的動機づけ」が深く関わっています。
これは、外からの報酬や評価ではなく、「自分の中から湧き上がる動機」で行動する力です。
子どもが「もっとやってみたい」「これは自分の好きなこと」と感じられるようになるには、自分の行動に意味があると実感できることが大切です。その実感を与えるのが、具体的で前向きなフィードバックです。
もちろん、毎回完璧な言葉がけをする必要はありません。
しかし、できるだけ「結果」よりも、「過程」や「挑戦」に目を向け、「どうやって取り組んだか」「どこを工夫したか」を一緒に振り返ることで、子ども自身が学びの意味を理解し、前向きなエネルギーに変えることができます。
NGな褒め方・叱り方に共通するポイント
子どものやる気や自己肯定感を育てるうえで、大人のフィードバックが逆効果になってしまうケースも少なくありません。
とくに注意したいのが、何気ない褒め方や叱り方が、子どもの成長を妨げてしまうことです。
「頭がいいね」「天才だね」といった能力を固定化する褒め方
一見ポジティブに聞こえるこの言葉は、「できることが前提」というプレッシャーを与え、子どもが失敗を避けるようになる原因になりかねません。
こうした褒め方を繰り返すと、「失敗=自分の価値が下がる」と感じてしまい、挑戦を避ける傾向が強まります。
また、叱り方についても、「なんでできないの」「また失敗したの」といった否定的な言葉は、子どもの自信を奪い、自己否定感を深める要因になります。
ミスや失敗の背景にある「どうしてそうなったか」「どう考えて行動したのか」といったプロセスに目を向けずに、結果だけを責めてしまうと、子どもは学ぶ意欲を失ってしまいます。
「どういう努力をしたのか」「何を考えて行動したのか」を意識する!
たとえ結果が思わしくなくても、そこに至るまでの姿勢やプロセスを認めることで、子どもは前向きに次の行動を考えるようになります。
「できた!」を引き出す言葉がけの工夫とは
子どもが「できた!」と自信を持って感じられる瞬間を増やすことは、やる気や自己肯定感を育てるうえでとても大切です。
そのために有効なのが、行動や思考に目を向けた具体的な言葉がけです。
成功の結果だけでなく、そこに至る過程を認める声かけが、子どもの中に「自分でやり遂げた」という感覚を生み出します。
例:
すごいね!
最後まであきらめなかったね!
このように、子ども自身がどのように取り組んだかを言葉にすることで、自分の努力や工夫に気づき、それが成功体験として積み重なっていきます。
また、子どもがつまずいたときこそ、前向きな言葉がけのチャンスです。
「まだできない」ではなく「もう少しでできそうだね」「前よりも上手になってるね」といった声かけは、成長を実感させ、あきらめずに続ける力を育てます。
このような言葉がけを意識することで、子どもは「うまくやること」よりも「挑戦すること」や「学び続けること」に価値を感じるようになります。
結果的に、成功したときの「できた!」という実感も、より深く本人の中に根づいていくのです。
親や先生にできる!タイプ別・子どもの個性に応じた接し方
子どもの才能ややる気を引き出すうえで忘れてはならないのが、子ども一人ひとりの個性の違いです。
どの子にも効果的な“万能の声かけ”は存在せず、それぞれの性格や反応の傾向を理解したうえで、適切なフィードバックを選ぶことが求められます。
まず意識したいのは、子どもによって「響く言葉」が異なるという点です。
ある子は、はっきりとした言葉で褒められることでやる気を出しますが、別の子はあまり注目されすぎると逆に萎縮してしまうこともあります。つまり、同じ褒め言葉でも、相手の感じ方によっては逆効果になりうるのです。
また、慎重で自己評価の低い子どもには、結果を問う前に「よく頑張っていたね」「ここまでやったことが素晴らしいよ」と、プロセスを丁寧に認める声かけが効果的です。
一方、活発で自信に満ちた子どもには、「次はここを工夫してみよう」といった前向きなチャレンジを促すフィードバックが、さらなる成長を後押しします。
重要なのは、子どもの行動をよく観察し、「この子はどんなときに力を発揮するのか」「何に対して意欲的になるのか」といった傾向をつかむことです。
個性を理解することは、フィードバックをただの言葉で終わらせず、心に届く対話にするための第一歩です。
さらに、親や先生自身が「この子にどう成長してほしいか」ではなく、「この子が何を大切にしているか」に目を向けることで、より子どもに寄り添った接し方が可能になります。
内向的な子 vs 外向的な子、それぞれに合う声かけ
子どもへのフィードバックで大切なのは、その子の性格や傾向に合った言葉を選ぶことです。
特に「内向的な子」と「外向的な子」では、やる気を引き出す声かけのアプローチが大きく異なります。
まず、内向的な子どもは、慎重で周囲の反応に敏感な傾向があります。
注目されすぎると緊張してしまったり、自信を持ちにくかったりすることもあります。
そのため、「みんなの前で褒める」よりも、「一対一で静かに声をかける」方が心に響きやすいです。
「今日の発表、すごく丁寧に話せていたよ」「あなたらしい考え方でとても良かった」といった、努力や個性に焦点を当てた具体的な言葉が有効です。
一方で、外向的な子どもは、人との関わりや注目されることに喜びを感じる傾向があります。
そのため、周囲の前で褒められたり、グループの中で役割を与えられたりすると、やる気を引き出しやすくなります。
「みんなの前でも堂々としていたね」「リーダーシップを発揮していたね」といった言葉が、自信と行動力の強化につながります。
どちらのタイプにも共通して大切なのは、「どうしてそれがよかったのか」を明確に伝えることです。
本人が自分の価値を理解できるようなフィードバックが、やる気や才能の育成に直結する!
得意分野がない子へのフィードバックの工夫
「この子にはまだ得意なことが見つからない」「何を褒めればよいかわからない」
――そんな悩みを抱える親や教育者は少なくありません。
しかし、 “得意なこと”は生まれつき備わっているものというより、環境や関わりの中で育っていくものです。
そのため、まだ目に見える形で才能が現れていなくても、適切なフィードバックを通じて、子どもの可能性を少しずつ引き出すことができます。
まず大切なのは、「できる・できない」に焦点を当てすぎないことです。
結果が見えにくい場面でも、「集中して取り組んでいたね」「最後まであきらめなかったね」といった過程への声かけを続けることで、子どもは自分の行動に価値を見出すようになります。
また、どんなに小さな行動にも意味を見つけて言葉にすることがポイントです。
「友達に優しくしていたね」「静かに話を聞けていたね」といった日常の行動に気づき、それを丁寧にフィードバックすることで、「自分には人を助ける力がある」「人の話を大事にできる自分がいる」といった自己認識が育っていきます。
得意分野がないと感じるときこそ、子どもの中にある小さな芽に気づき、育てる視点が大切!
学習や成長に直結する!フィードバックの実践例
理論だけでなく、日々の生活や教育現場でどう実践するかが、フィードバックの効果を大きく左右します。ここでは、家庭や学校などで実際に使えるフィードバックの具体例を紹介しながら、学習や成長を促す方法を考えていきます。
まず家庭では、日常の会話やふれあいの中に自然な形でフィードバックを取り入れることが大切です。たとえば、子どもが宿題に取り組んでいるときには「今日も時間を決めて始められたね」「昨日よりも漢字の形が整ってきたね」と、小さな進歩に気づいて言葉にすることがポイントです。こうした声かけは、「見てもらえている」「努力が認められている」と子どもが感じることで、やる気や自信を育てます。
また、失敗したときや結果がふるわなかったときこそ、成長のチャンスです。たとえばテストで点数が低かった場合にも、「どこでつまずいたか一緒に見てみよう」「頑張っていたプロセスはしっかり伝わってきたよ」と声をかけることで、「失敗=ダメなこと」ではないという前向きな認識を育てることができます。
一方、教育現場では、子ども同士の関わりを活かしたフィードバックも有効です。たとえば、グループ活動後に「誰がどんな工夫をしていたか」を互いに伝え合う時間を設けると、他者の視点を通じて自分の強みに気づくきっかけになります。また、教師が一方的に評価するのではなく、「ここを工夫していたね」と個々の努力を言語化して伝えることで、指導が“評価”から“育成”へと変わっていきます。
さらに、子ども自身に「今日の自分の良かったところ」「頑張った点」を振り返らせる時間を設けることで、自己認識力と自己肯定感の向上にもつながります。
このように、フィードバックは特別な時間にだけ行うものではなく、日常のあらゆる場面に取り入れられる習慣です。次章では、家庭と教育現場、それぞれの場面での具体的な声かけやコーチング例をより詳しくご紹介していきます。